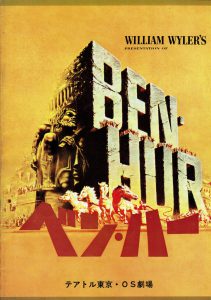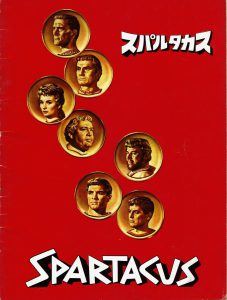ハリウッドで“史劇”というジャンルが大流行したのは、1950年代後半から1960年代にかけてのこと。その背景には、50年代に入り家庭に普及が進んだテレビによって、家に居ながらにして映像作品を見ることが出来るようになったことがある。
つまり、観客を奪われることを死活問題と捉えた映画界側が、テレビ画面では味わうことの出来ない大スクリーンでの迫力あるスペクタクル映像を志向し、それに最も適したジャンルが、巨大なセット、大勢のスターの競演、何千人ものエキストラによって描かれる叙事詩的歴史大作だったのだ。
『十戒』劇場パンフレット(筆者私物)
セシル・B・デミル『十戒』のハリウッド的“大嘘”とは?
ハリウッド最初期からの巨匠セシル・B・デミル監督は、サイレント映画時代に数々の史劇(エピック・フィルム)で名を成した。しかし、テレビ時代の到来で再びこのジャンルが脚光を浴びることとなった1956年、自身のサイレント期の代表作『十戒』(1923年)を、さらに大掛かりのカラー超大作としてリメイクすることを決意した。
Comparing Cecil B. DeMille's silent 1923 version of The Ten Commandments with his 1956 remake pic.twitter.com/Ku4zzo8IQi
— Silent Movie GIFs (@silentmoviegifs) July 4, 2020
その作品『十戒』(1956年)は、新進気鋭の二人の大型スター、チャールトン・ヘストンとユル・ブリンナーを筆頭に、ヴェテランから若手まで当時のスターたちが大挙出演した大作中の大作。――だが、史劇にはサイレント映画の時代には誰も気づかなかった大きな問題があった。それは言語の問題で、本来であればヘブライ語やエジプト語やラテン語でなければおかしいのだが、ハリウッド製の映画だから当然、台詞はすべて英語になる。
『十戒(リバイバル版)』劇場パンフレット(筆者私物)
この大嘘は、洋画に対して英語なのだから日本人はさほど気にならなかっただろうが、考えてみれば『テルマエ・ロマエ』(2012年)で古代ローマ人が日本語を喋るのと同じくらい無理のある設定だ。さらに『十戒』では、モーゼが手に取る十戒が刻まれた石板には古代ヘブライ語が刻まれているから、喋る言語と書き文字との齟齬という問題もある。
同じような問題は最近の映画でも見受けられる。日本の忠臣蔵に基づいた『47RONIN』(2013年)では、キアヌ・リーヴス以外の主要キャストはみな日本人俳優で喋る言語は英語だが、中世のお伽の国のような世界観で統一されていて、台詞が英語なのは違和感ない。でも、討ち入りの為の誓詞血判をするシーンになって突然、書かれる名前の文字が日本語になっていて、どうにも違和感がぬぐえない。
『ベン・ハー』と『スパルタカス』で市民権を得た“英語を喋る”古代ローマ人!
その後、チャールトン・ヘストンは、サイレント映画版『ベン・ハー』(1928)で助監督を務めたウィリアム・ワイラー監督がリメイクに挑んだ、同名作品のタイトル・ロールで不動の人気を獲得。作品はアカデミー賞史上最多11部門独占の快挙を成し遂げ、史劇(またの名を“剣とサンダル物”)をハリウッドで最もホットなジャンルへと押し上げた。
『ベン・ハー』劇場パンフレット(筆者私物)
このカラー超大作版『ベン・ハー』(1959年)の主役の座を狙ったのが当時の大スター、カーク・ダグラス。彼は直談判しに行ったが、ワイラー監督は「主役はヘストン」と決めていて、ベン・ハーの旧友にして宿敵となるメッサラ役を打診されたものの、ダグラスはこれを拒否。代わりに自らがプロデューサーを兼ね、自身の制作会社<ブライナ・プロ>で1200万ドルもの巨額の制作費をつぎ込んで、『スパルタカス』(1960年)のタイトル・ロールを演じることにした。
『スパルタカス』劇場パンフレット(筆者私物)
ところが、同時期にユナイト映画でも同じスパルタカスを題材とした『剣闘士』という企画をユル・ブリンナー主演で進めていたことが判明。競作とするか、どちらかが手を引くか、二つの企画を合体させてダグラスとブリンナーの共演とするか、駆け引きが繰り広げられていたが、結局は監督にアンソニー・マン、キャストにローレンス・オリヴィエ、チャールズ・ロートン、ピーター・ユスティノフという重量級を揃えたダグラスに軍配が上がり、ブリンナーは撤退。代わりに『荒野の七人』(1960年)に取り組むことに……。
ダグラスは『スパルタカス』の脚本を、当時ハリウッドで“赤狩り”のブラックリスト入りしていたダルトン・トランボに依頼。そのため反共産主義勢力がボイコット運動を始めたが、時の大統領ジョン・F・ケネディが予告なしに『スパルタカス』を映画館に見に行って好意的なコメントを残したことで風向きが変わり、これによってハリウッドに長く存在したブラックリストは有名無実化した。その経緯は『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』(2015年)に詳しく描かれている。
ともあれ、『ベン・ハー』と『スパルタカス』という超大作二本がいずれもハリウッド史上に残る傑作として圧倒的な成功を収めたことで、古代ローマ人が英語を喋る“剣とサンダル物”が市民権を得た、と言えそうだ。
『スパルタカス』を巡る伝説の数々
『スパルタカス』には一冊の本が書けるほどのエピソードがあるのだが、よく知られているのは、撮影開始後にプロデューサー兼主演のカーク・ダグラスの権限で監督のアンソニー・マンが解任され、代わりに当時まだほとんど無名で、ダグラスの製作・主演による『突撃』(1957年)を演出した若干31歳のスタンリー・キューブリックが大抜擢されたこと。
In February 1959, #StanleyKubrick signs on to direct #Spartacus following a phone call from Kirk Douglas himself. It would be the last film he would be a 'director for hire' without being involved in the screenplay and film research. pic.twitter.com/cveAnmtenp
— Stanley Kubrick (@StanleyKubrick) February 4, 2022
実は、最終的にダルトン・トランボが(偽名ではなく)本名でクレジットされたワケは、現場で脚本を変えつつ演出した自分を「脚本家としてクレジットしろ」と主張したキューブリックに怒ったダグラスが、それならばいっそブラックリストを無視しよう、と判断した結果だ。
キャスティングをよく見ると、ローマ人の役はオリヴィエにロートン、ユスティノフとすべて英国人俳優が、奴隷役にはダグラス以下全てアメリカ人俳優が演じるなど、プロデューサーとしてのダグラスのこだわりは随所に感じられる。
1959: Thirty-year-old #StanleyKubrick has four feature films under his belt when he receives a call from Kirk Douglas asking him to direct a new film he’s acquired the rights to. The future classic - #Spartacus. pic.twitter.com/noYLBMublb
— Stanley Kubrick (@StanleyKubrick) May 17, 2022
また、最後の戦いに敗れて捕虜となった奴隷たちに対して、将軍クラサスが「スパルタカスがどの男かを教えればみなは助けてやる」と密告を奨励したのに対して、何千人もの奴隷たちが口々に「アイ・アム・スパルタカス!」と叫ぶシーンの音声は、ミシガン州立大学のアメフト・チーム<スパルタンズ>に協力を依頼し、スタジアムを埋め尽くしていた熱狂的なファンたちに試合の合間のハーフタイムに叫んでもらったものを用いたという。ダグラスがプロデューサーとしても優秀だったことを示すエピソードだ。
To create the sound of large crowds, @StanleyKubrick's crew recorded spectators at a Michigan State – @NotreDame college football game. Kubrick had them shout, "Hail, Crassus!" & "I'm Spartacus!" #AFIMovieClub pic.twitter.com/v6jTGZqNph
— AFI (@AmericanFilm) May 5, 2020
解任された大物監督が『エル・シド』『ローマ帝国の滅亡』でリベンジ!
一方、解任されたアンソニー・マン(彼の演出した部分も『スパルタカス』には残っている)は、その後、同じような史劇超大作二本を監督して実力を証明した。――それが『エル・シド』(1961年)と『ローマ帝国の滅亡』(1964年)で、前者はそのタイトルが醸し出すイメージの通り『ベン・ハー』の夢を再現しようとした企画で、主役の伝説の最高戦士も同じチャールトン・ヘストン。舞台は古代ローマではなく11世紀のスペイン(カスティーリャ王国)だった。
後者はもちろん“剣とサンダル物”のオールスター・キャストの大作で、主役リヴィウスには『ベン・ハー』で(カーク・ダグラスが蹴った)メッサラ役を演じたスティーヴン・ボイドが扮している。この二作のプロデューサーは共にサミュエル・ブロンストンで、いわばブロンストンが自らの『ベン・ハー』と『スパルタカス』をアンソニー・マン監督に作らせた形なのだが、ヒロイン役はお気に入りのソフィア・ローレンに両作品とも務めさせている。
James Mason, Sophia Loren and producer Samuel Bronston during a break from filming on the set of The Fall of the Roman Empire (1964) pic.twitter.com/rNLfQUAKA5
— Old HollywoOoOoOoOod ? (@TheOldHollywood) March 30, 2022
CG無しの小道具やエキストラが“史劇(エピック・フィルム)”の証!
史劇(エピック・フィルム)というジャンルがこの時代に流行したのは、そのスケール感ゆえだったことは最初に述べた。
具体例を示すと、たとえば『スパルタカス』では小道具も装置も本物が必須とのことで、50万ドル相当の銅像、兵器、家具、3,800着のローマの軍服、その他100種の小道具総計27トンが外国から借り受けられ、撮影のために新たに発注して製作された鎧(アルミ製)7トン分を輸入している。戦闘シーンで戦う8000名の兵士や奴隷たちには、スペインの軍隊(マドリッド地区の歩兵たち)が動員されている。
『ローマ帝国の滅亡』では、1500頭の馬がスペインとポルトガルから集められて、戦闘シーンで転倒することなども含めた訓練が行われ、実際の戦闘シーン(四つの軍隊が入り乱れて戦うシーン)では1200の騎馬兵を含む8000名の兵士たちの戦いが実際に撮られているが、古代ローマ人は馬に乗るのにあぶみを使わなかった史実に即して、カメラからは見えないL字形のあぶみが特別に考案された。
ほかにも、たとえば雪深いアルプスでの蛮族たちとの闘いの前線に赴いた皇帝や延臣たちが身にまとうケープは、宮廷の伝統に則って中部イタリアのアブルッツィ山脈に生息する狼たちのつやつやした毛皮で作成することとし現地の猟師たちに特別賞与を支給することで狼たちを捕獲して毛皮を調達し、フローレンスで衣装として仕立てられたという。
こうした、圧倒的な物量とセットや人的側面でのスケール感、そして本物志向というのが、この当時の映画作りのキモなのであって、CGによってコンピュータの中で何でも作り出せてしまう現代の映画製作とは根本的に異なる。――筆者が過去記事でも言及した“カニカマ理論”を最もわかりやすく説明できるのが、史劇というジャンルなわけだ。
エピック・フィルムの全アクションを演出した「ヤキマ・カヌート」とは?
最後にひとつ、あまり知られていない事実を紹介しよう。――『ベン・ハー』でチャールトン・ヘストンとスティーヴン・ボイドが四頭立て馬車同士で競い合うスペクタクル・シーン、『スパルタカス』でカーク・ダグラスが黒人奴隷ウディ・ストロードと死闘を繰り広げるシーン、『エル・シド』でのヘストンとクリストファー・ローデスによる大観衆の前での一騎打ちのシーン、『ローマ帝国の滅亡』で四つの軍隊が入り乱れて戦うシーンを含めたアクション・シークエンスのすべてを実際に演出したのは実は同じひとりの人物で、その名をヤキマ・カヌートという。
The iconic chariot race in William Wyler's BEN-HUR ('59) took 10 weeks to shoot and was coordinated by Yakima Canutt. It has influenced filmmakers to this day including George Lucas who said this scene inspired the pod race sequence in THE PHANTOM MENACE ('99). #31DaysofOscar pic.twitter.com/73Ir1ogafr
— TCM (@tcm) April 3, 2021
カヌートは、元はロデオの世界チャンピオンで、サイレント映画の時代からアクション・スター兼スタントマンとして活躍。戦前だと『駅馬車』(1939年)でジョン・ウェインのスタントダブルとして疾走する六頭立ての駅馬車で馬車から馬へと飛び移るシーン、『風と共に去りぬ』(1939年)でクラーク・ゲイブルのスタントダブルとして炎上するアトランタ市街で崩れ落ちる建物から間一髪、馬車でヴィヴィアン・リーを救い出すシーンなど、有名作品の有名なシーンをほとんど演じた伝説の人。
John Ford's STAGECOACH was released today in1939. It includes a dangerous stunt by legendary stuntman YAKIMA CANUTT. pic.twitter.com/tcavdl5IyY
— FilmFrame (@FilmFrameATRM) February 10, 2021
その卓越した才能と技術はスペクタクル史劇で最も頼りとされ、『ベン・ハー』や『エル・シド』、『ローマ帝国の滅亡』では第二班監督としてクレジットされ、実際のところ『ローマ帝国の滅亡』では総撮影日数143日のうち、ほぼ半分に当たる69日はカヌート演出によるアクション・シークエンスの撮影だった。
文:谷川建司
『十戒』『エル・シド』『ローマ帝国の滅亡』はCS映画専門チャンネル ムービープラス「黄金のベスト・ムービー」で2022年10月放送